いつしかの箱 その4
長田さんは言う。
「自閉症の子って、ハンディキャップを抱えているという面に焦点が当たりやすいけど、本当はもっと違うことが見えるものなんですよ。あえて言えば、人の原始的な部分、意識や意思よりももっとストレートな根っこの部分……なのかな。彼らはそれを隠さず、さらけ出しているように、僕には見えます」
長田さんが一緒に遊んでいた子たちは、彼曰く「コミュニケーションがあまりくどくなかった」。たとえば人の目を気にせず、一方的に相手を観察している。そして、この人はちょっと信用できるかもしれないと思えば、近づいてくる。自分の感情や直感に正直なようだ。長田さんも、彼らに対してそうしていた。子供たちに何かしてあげようという押し付けはしなかった。
大勢の子供たちがいる集団のなかに「お兄さん」であるスタッフが入るとしよう。すると普通は「お兄さん」の立ち位置が、自然と決まる。仮に野球をやる場合、スタッフはピッチャーやキャッチャーの任務に就く。子供たちもスタッフに「お兄さんは力があるんだから、ピッチャーをやってよ」などと言い、大人への信頼半分、あなどり半分をもって、役割を依頼してくる。でも、長田さんが付き合っていた自閉症の子たちには、それがまったくなかった。子供たちと長田さんの関係はつねに対等だ。互いの存在を尊重しつつ、心地よい距離を保ち続けていた。
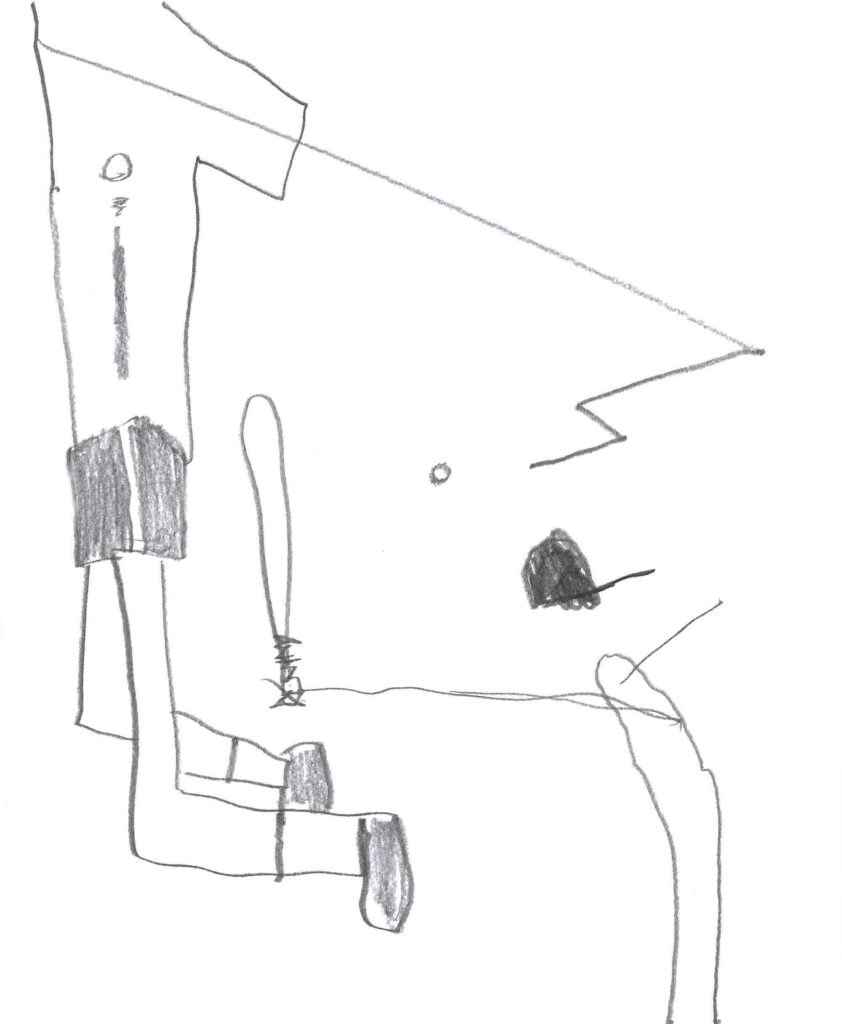
長田さんはK君をずっと観ていた。K君は学童クラブのなかで、精神的に安定しているようだった。自分の感情に対して、素直に過ごせていたのかもしれない。
幼少期、K君は自分の遊びを始めると、外の世界をシャットアウトして、その遊びに集中していた。たとえば埃を見つけたら、それをずっとカリカリ掻き出したりしている。まわりの目は気にしない。
とはいえ、他人とのコミュニケーションがないわけではない。友達のところへ行って(長田さんから見れば訳のわからないタイミングだが、)笑ってみたり、トントンと肩を叩いてみる。自分の作っているものを他の子に壊されたら、怒ったり、泣く。スタッフにも愛されていた。楽しそうで、よく笑っていた。数年後、野球にのめり込んでいたときも、自分が打ち込める存在を見つけた喜びがあったようだった。
K君は無理せず、日々何かを探究する自由な感覚をもっていた。それは長田さんに「あんなふうになりたい」と思わせるものだった。K君たちの世界を知った長田さんはそれ以後、規範や世間体よりも、自分の感覚に正直に生きること、そして自然体でいることをとても大切にしている。
学童クラブのアルバイトを辞めて絵本作家となった今でも、長田さんはK君が残した「はまぐり」や「しろなす」の謎を心の片隅に留めている。
「僕はK君の『はまぐり』や『しろなす』の謎が好きです。でもなぜ『しろなす』を書き続けたのか、その答えが知りたいわけではありません。良い謎は、謎のままであるほうが素敵なんですから。何にも回収されないから、受け手はその謎の背景を、いくらでも勝手に想像できます。言葉で解明したり、科学的な検証をしたり、学会で発表する必要はない。その気分って、絵本と似てますよね。絵本があって、読者は絵本を一方的に見ることができて、作者の世界に浸って、思いも寄らない自分のなかの変化を楽しめるってことです」
長田さんはこうした「謎」から受けた印象を、人生の別のタイミングで体験したことと重ねる癖があるという。たとえば普段の生活で、ふとした瞬間に目にとまった物を気にしてしまうことがある。すると何気なくやったその行動が、「しろなす」の記憶を呼び起こす。「しろなす」の謎と、自分の理由なき行動から受ける印象が、感覚的に繋がるのだ。
人生の過去の一点と現在が繋がって、新たな何かを発見する。自分にとって何が気になるものなのか、何がおもしろいのか、何を良しとするのか……。そうやって長田さんは、いつも自分自身を見つめ続けている。
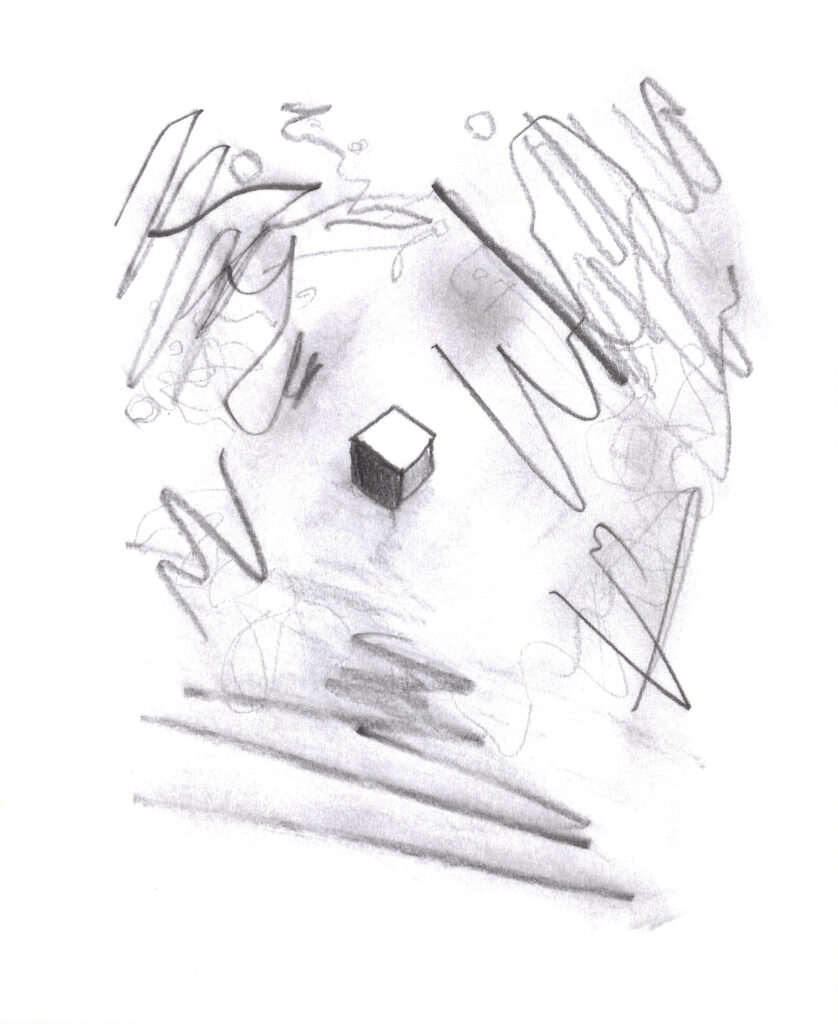
絵 長田真作 文 織言堂
